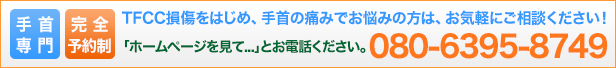バドミントン上達のヒント
先日バドミントンをしていて、あるメンバーの人に
「しまちゃんは調子が悪い時は、すくむようにフォームが崩れるよね」
と言われました。
なんとなくそんな気はしていたものの、はっきりとは認識していませんでした。
はたから見てそう見えるなら、間違いないのだろうなと。
このヒントが私の中で、点と点がつながるようなヒントになりました。
バドミントンをしばらく休んで久しぶりにやると、なぜか割と調子が良く、
連日続けているとだんだんミスが増えて面白くなくなってしまう。
これ、筋肉疲労で、筋肉が短縮してしまうことによってフォームが崩れているのではないか?
という仮説が出来ました。
バドミントンの時、肩が痛くなることも多いのですが、筋肉のケアをしていてもわりとよく痛くなる。
いつもは肩関節の内旋外旋の動きに関わる筋肉をケアしていたのですが、今回のヒントを元に、
「広背筋」と「大円筋」
もケアをしてみました。
いわゆる脇の下の筋肉です。
そうすると今まで取り切れなかった肩の違和感がさらにすっきりしました。
「力を入れるつもりもないのに入ってしまうのは、筋肉の固まり癖のせいだったのでは?」
そう考えると、しばらく休むと調子が良くなることのつじつまが合います。
球を打とうとしたとき、無意識に脇を閉じてしまう。
そうすると、縮こまったいびつなフォームになるのです。
コンパクトなスイングと、縮こまるスイングは違いますからね。
このケアを続けて、調子が維持できるようになれば、ちょっとしたスランプ脱出になるのではないかと。
肩の痛みって一言で言っても、関連する筋肉沢山ありますね。
自分の体を使って実験するのが一番良い勉強になります。
ゴルフもテニスもバドミントンもクライミングもぜーんぶ毎日やりたい、本当は。
だから、私はケガとか故障はウエルカムなのです。
歳を取ってくるとあれこれと痛みが出やすくなるかもしれないけど、それらの一つ一つをクリアしていけば、好きなことを体の痛みであきらめなければいけないなんてことは無くなりますからね。
ほとんどの関節の痛みは、筋肉のケアで良くなる。
嘘偽りなくそう思います。
痛みは主観的なもの。
自分の体で勉強したことは、どこの教科書にも書かれていない生の情報。
だから、誰にもまねのできない領域になれるのです。
(医学的根拠はない)
医学的根拠よりも、結果の方が大事ですからね。