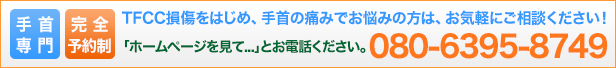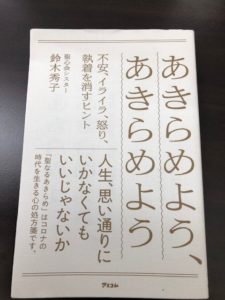あきらめようあきらめよう
あきらめることは二つの意味がある
諦めると、明らめるだ。
明らめるというのは、明らかに眺める。
つまるところ現状を受け入れるという事。
そうかそうかと現実を受け入れる。
そして、さてどうしようと考える。
二ーバーの祈りとして有名なフレーズがある。
神よ、変えることのできないものを静穏に受け入れる力を与えてください。
変えるべきものを変える勇気を、そして、変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてください。
というもの。
変えられないものを変えようとすることは苦しみを生み続ける。
だから、どちらなのか明らかに眺めるのです。
そうかそうかと受け入れたら、自分がどうすべきか見えてくる。
以前読んだ書籍、諦める力でもそのような話がありました。
明らめることは大事。
その結果、諦めることになるかもしれないし、戦うことになるかもしれないし。
執着を手放すことで楽になれることもある。
私もこの本を手に取っているくらいだから、色々苦しんでいるのです。
人の苦しみを扱う仕事だから、希望を与えられることもあれば、その苦しみに飲み込まれそうになることもある。
私が諦めるのは簡単だけど、ただそれだけだと突き放しているだけになることもある。
とはいえ、力になれる部分は限られているし、踏み込みすぎれば課題の分離という点で、おせっかいにもなる。
基本的に私は言わなくていいことを言って、問題を起こすタイプ。
時にそれは必要悪になることもあるし、本当に必要なく人を傷つけることもあるし、不快にさせることもある。
そんな自分を諦める。
長所と短所は紙一重で、上手くハマればそれが武器になる。
短所を無くそうとすると、長所が無くなることにもつながることも。
吉田松陰が高杉晋作に対してもそのような視点で接したようです。
吉田松陰自身も、常識人とは全く言えない、ある種の狂人。
未熟さを受け入れることで、他人の未熟さも受け入れられるようになる。
苦しい時は手放すことも覚えないといけない。
というより、手放すより他なし。
自分と他人は違うということは受け入れる他なし。
自分と同じことを期待しても、苦しむだけ。
この世は不条理がたくさんある。
しかしそれを嘆いても仕方がない。
何で自分はこうなんだ!と憤ってみても仕方がない。
色々勉強すればするほどたどり着くのは、この世は魂の修行に来ているという話。
今の環境で出来ることをやって、魂を磨いて、この世を去っていく。
死生観を磨くことが、執着を手放すことにもなり、苦しみからの解放にもなるのだと思う。